2021年7月22日から25日にかけて、計3泊4日間飯豊山を彷徨い歩いてきました。
今回の記事はその二日目、今日は初日の宿である梅花皮小屋から飯豊本山へと向けて歩きます。
この登山をする前に、様々な雑誌やWeb媒体で飯豊山を歩いた方々の記事を見てきました。その多くには飯豊山が真に楽しめるのは本山から北股岳までの稜線にあると語られています、本日の道中はまさにその核心部を歩くわけですが、そこは花と雪渓に彩られた大山脈のど真ん中でした。
コバイケイソウ、シラネアオイ、ニッコウキスゲ、チングルマ、ハクサンイチゲ、マツムシソウ、この山に咲く花は素晴らしく、その群生の奥に見える稜線は誠に偉大です。
二日目、午前の早い時間は悪天の状態でしたが、天気は徐々に好転し御西小屋へ到着するころには空一面に青空が広がり、飯豊山の南北へと連なる長大な稜線を見渡すことが出来ました。
また、ニッコウキスゲの群生に目を輝かせた初日に対し、二日目は当たり年を迎えたコバイケイソウが咲き乱れる稜線が姿を現します。
好天続きの飯豊山、二日目は核心部の往路です。
今回の飯豊山登山の概要


雲の朝、梅花皮小屋から本山へ向かう

2021年7月23日、午前3時50分梅花皮小屋。
飯豊山梅花皮小屋の朝です、おはようございますRedsugarでございます……。
午前3時頃からごそごそと動く音が聞こえ始めたため、目覚ましよりも早く目覚めてしまいました。
そこからボケーッとした後に準備を開始、すると見る見るうちに人々が起き始め朝の支度をしていきます、何時しか小屋の二階は朝食の団欒を楽しむ人々でいっぱいになっていました。
飯豊山を南に向かって縦走する人の多くはこの時間帯に起床するようですね。

午前4時20分、梅花皮小屋出発。
軽めの朝食にソイジョイを飲み込み、水分を補給し小屋の外へと出てみれば……ガスの向こうにかろうじてご来光に染まる空が見えます。この日の夜明けは天気が悪く、晴れ予報だけど全く晴れていないという悲しい状況が続きます。
 redsugar
redsugar最初小屋を出たときは本当に気分が暗かった、本当に今日晴れるんかいと。






雲は流れているので晴れているような景色も撮れるのです、ですがすぐさま流れてくるガスに景色は奪われてしまいます。乳白色に染まった空を眺めながら、今日の目的地である本山小屋は晴れてほしいと願い歩みを進めます。


梅花皮小屋を出発して烏帽子岳へと向かう道中は雪渓の端を歩くような地点があります、本山までは数か所雪渓を渡るところがあるのですが、これが明け方だとトゥルントゥルンなんですね。
滑って転べばそのまま下まで滑っていきそうな恐怖があるので、慎重に雪渓を渡っていきましょう。


午前5時30分、烏帽子岳。
ガスの中雪渓を渡り登ってきたのは烏帽子岳、本当はここから飯豊本山を真正面にみるつもりだったんだけど……、超曇ってるので視界はゼロ。それに湿った空気が身体を濡らすのが不快でしょうがない。
泣き言を言っていても仕方がないので先に進みますが、本来であればここは眺望がいいところ。


烏帽子岳から先も雪渓を渡ります、端を歩くのは変わりないのですが、足跡が薄いことや氷の表面が磨かれているところもあるので、足元は慎重にチェック。心配ならチェーンスパイクがあるといいかも。



僕が歩いた7月後半でも雪渓渡りは数度発生していて、結構大変でした。雪渓がなくなる秋口とかはもっと歩きやすかったのかも。


霧が降りた稜線ですが、悪いことばかりではありません。高層湿原を横切る時にはうすい靄がかかった景色が幻想的に見えることもあるのです。






霧の中で風に揺れる花々も、晴れた空の元とは違い幻想的な雰囲気を纏います。特に驚くべきはコバイケイソウ、辺り年だったため烏帽子岳から先で多くの群生が僕を迎え入れてくれました。



飯豊山縦走でここまでのコバイケイソウの群生を何箇所も見れるとは思いませんでした、ただ若干……花がたくさん咲いているところは香ばしいにおいが……キツイ。


コバイケイソウの花は見た目が良く群生地で一斉に開花すれば圧倒的な景色を見せてくれます。でもこの花はとても強い毒性を持っていることと、においが結構きつい(アンモニア臭がする)
写真で見ると景色はいいんだけどなぁ……。


烏帽子岳から天狗の庭まで、しばらくの間コバイケイソウを眺めながら歩みを進めていきましょう。


目の前は延々ガス、明るさ的にこの雲の高度は稜線と同じくらいで空は晴れていると推測されます。稜線に張り付く雲ほど鬱陶しいものもないので早く晴れてほしいです。






晴れないなぁと項垂れながら歩き続けていると、僕の願いを察知したように時折視界が開け始めました、天気が好転している……。時折見える烏帽子岳の山肌に期待が上がります。


烏帽子岳から天狗の庭までの稜線には時折沼や池塘が現れます。
これは御手洗の池の周辺で、この辺りでようやく天気が良くなってきました。
天狗の庭、青空の飯豊山は天下無二の景色






午前6時40分、御手洗の池。
烏帽子岳から天狗の庭の間にある休憩スポット的な場所がこの御手洗の池です。あいにくのガスで景色は見えないんだけど、この御手洗の池から少し進んだ一から烏帽子岳を振り返るととても迫力のある山肌が見えるらしく期待していたのですが……ガスで見えませんでした。
代わりに谷底へと一直線に伸びる雪渓や、麓の雲海を見ることはできたんだけども。


かろうじて開けた視界の奥に見える烏帽子岳の山肌は確かに迫力がある、マッシブな陰影を携えていてかっこ良さそうだ。雲が少なければその独特な威容を余すことなく拝みたかったところ。


明け方は日も寝ているので、稜線に浮かび上がる木々を眺めながら歩くと楽しい。
結構特徴的というかぴょんと飛び出た木々がいたりするものです。


天狗の庭へと進んでいくと見る見るうちに雲が取れていく、これはやったかと思ったのですが……。



この後また烏帽子岳に雲がかかってしまった、無念。






午前7時25分、天狗の庭。
ガスの中を進み天狗の庭にやってきてしまいました、飯豊山稜線の展望スポットということでここをすごい期待していたんだけど残念ながら往路はガスの中。復路に期待です。
天狗の庭は広い尾根の中に池塘が点在し、笹ではなく高層湿原が広がる一体です。休憩場所もあるためここで足を休める人もいそうですね。


烏帽子岳方面はガスだけど新潟県側は晴れていて青空が垣間見えます、やはり上空は雲がないけど稜線付近の高度には雲が多いようです。






天狗の庭を出立したタイミングでようやく天気が回復傾向となり稜線に日が差し込んでくれました。それと同時にぐんぐん気温も上がっていきます、灼熱の飯豊山が目を覚ましますね。
太陽が姿を現してから、シラネアオイやニッコウキスゲが息を吹き返したかのように煌びやかに輝き始めました、登山者の僕の顔にも笑顔が浮かぶ。



やった!!!花だ!!!青空と花が見れる!!ヤッターーー!


大日岳方面の雲が薄く山肌が徐々にあらわになります、大日岳の山肌も大変迫力がある景色です。


新潟県の山とも東北の山とも微妙に雰囲気が違うと感じる飯豊山の山肌。雪で削られつつも丸くない、鋭さを残したような斜面が続く。




本山側は雲が取れ奇麗に晴れた山肌を拝むことができました。この瞬間が今日一番テンションが上がった瞬間です、烏帽子岳方面はまだガスの中だけど、本山がこんなにきれいに見えるなんて……と感動した。


ただ手放しで喜んでも居られない、大日岳を掠めるように流れて行く雲などを見ていてもこの晴天は長続きしないことは間違いないのです。この与えられた晴天を逃すことなく、景色を目に焼き付けていきます。


烏帽子岳方面もようやく雲から顔を出してくれました、目の前のあの山からはるばる歩いてきたと考えると感慨深いものがある。そして烏帽子岳……かっこいいなぁ。


この稜線は写真にも写っているようにコバイケイソウの群生が非常にたくさん咲いていて、ちょっと進んでは写真を撮影してしまう悪魔の稜線でした。


烏帽子岳までの稜線はとても美しく、ここを飯豊山の核心部という人の気持ちはよくわかる。


でも個人的に飯豊山で好きなのは天狗の庭から本山までのこの道、穏やかで長大な道が本山まで続いていきます。目の前に見えるのは御西小屋、大日岳を朝市で目指す登山者などが宿泊する避難小屋です。
この避難小屋は立地がいいため多くの登山者が訪れます、しかし宿泊可能人数が少ない小屋でもあるので日によってはギュウギュウになってしまうことも。



僕が歩いた日付では最終日以外はすし詰め状態で寝ることを余儀なくされたとか……、恐ろしい……。
そして御西小屋は稜線の小屋ゆえの宿命といいますか……、水場がかなり遠いことと、トイレが悪魔のトイレであることが注意点です。梅花皮小屋や本山小屋のようなきれいな洋式ではありません、北海道式の竪穴式ニーハオトイレです。


御西小屋まであとわずかというところ、本山方面の開けた視界に広がる景色は最高の一言。見てくださいこの穏やかな稜線を……、最高じゃないですか。雪に削られ優しく穏やかな丸みを帯びた稜線、そこに走る雪渓の後、立体的に浮かび上がる陰影、飯豊山の美しい稜線が今ここに姿を現しました。



僕が稜線ソムリエだったらこの稜線は推せる。


コバイケイソウと稜線を撮影、先に進みたくても景色が良くてなかなか進めない。


何といっても目の前には花、花、花。足元にはチングルマ、イワカガミ、シラネアオイなどが咲き、ニッコウキスゲやコバイケイソウが草原の向こうでゆらゆらと揺れているのです。



イッツァ ヘヴゥン……ッ!
御西小屋、飯豊山核心部の稜線歩き






午前8時40分、御西小屋。
稜線を進み憧れの山小屋御西小屋に到着しました、鱗雲は出ているけども空はまだ晴天。
この御西小屋で少し休憩した後、本山小屋を目指したいと思います。小屋ではドリンクの補給が可能です、CCレモンとかコーラを購入することができます。


「小屋番さんがいないな……?」
飲み物を買おうと小屋番さんを探しても見当たらない、ふと下の雪渓を見てみると何やらバケツ一杯に雪を入れて登ってくる人が……、真っ黒に焼けた顔つきは間違いなく山の人、小屋番さんその人でした。






本山小屋方面と梅花皮小屋方面からの登山者双方が休憩する位置にある御西小屋は大変盛況で、大日岳登山を終えたと思われる人々が先ほどまで歩いた山を眺めながら談笑していたり。縦走する人々が地図を広げにこやかな笑顔を浮かべていたり、非常に和気あいあいとした雰囲気が流れている。
CCレモンで喉を潤した僕は小屋番さんと談笑し、これからの天気の話題に。すると小屋番さんはこれから雲が上がってきてあと数時間のうちに雨が降るという、ボクもそんな気がしていて、正午には雨が降ると考えていたのでこの日の大日岳登山はあきらめることにした。


青空が広がる御西小屋周辺、だけど山の天気は刻々と下り坂だったのだ。


CCレモンを飲み干し補給を終わらせたら本山小屋へ、なだらかでありつつもそれなりにアップダウンがある稜線を登り始める。目の前の道沿いには延々コバイケイソウが咲き続けているのがわかる。


午前9時5分、御西小屋出発。
御西小屋周辺もコバイケイソウの群生地、夏山らしい景色を思う存分楽しませてくれた。


遠ざかる御西小屋の向こうで大日岳が着々と雲に飲まれていく、それと時同じくして本山小屋へと向かう稜線も雲に包まれて行ってしまった。






飯豊山は標高の関係上低層雲がすぐに稜線にかかってしまう、それと同時に積乱雲がぐんぐん成長し正午から午後2時あたりで雨が降り始めてしまうことも珍しくない。そう考えていたが予想が的中しこの後土砂降りになりました。
ガスの中の本山稜線はそれはそれで美しいのだけど、雨と雷が怖くてとにかく先を急ぐ。
飯豊本山、奇跡の虹を見せてくれた日没


午前10時25分、飯豊本山。
飯豊本山にようやく到着したころには空気はややひんやりとしていて、本山到着の喜びもなくすぐに山頂を後にした。「快晴の山頂は明日の朝でいい!」と自分に言い聞かせて小屋へと急ぐ。
本当にこの時は雷が怖くて、正午前には小屋に入りたかったのです。






午前10時40分、本山小屋到着。
すっかり曇り切った飯豊山、本山小屋に到着したときには不思議と達成感で満たされていました。
往路が終わったという安堵だったんでしょう。晴れ間を拝むことができたのは一か所だけだったけど、あとはここから飯豊山荘に向かって帰るだけです。明日からは天気が今日よりもよくなるはずなので、今日よりもいい景色が拝めるはず……そう信じたい。
ちなみに、本山小屋は泊ってみるとわかるんだけどそんなにサイズが大きい小屋ではありません、人であふれた場合は神社の建物を開放するらしいけど……、それでも一つ前のポイントにある切合小屋のような収容人数ではないため、週末はよく収容人数オーバーになるとか。


現にこの日も到着時点ではスカスカだったけども、夕方になると満員になってしまった。
人が少ないタイミングで寝床を作った僕。初日に大量の汗をかいたタイミングで手ぬぐいが使い物にならなくなってしまい困っていたんだけど、ここで飯豊山オリジナル手ぬぐいが売っていたので購入、最後の一枚ということで縁起が良かった。
寝るときは着替えを入れたジップロックに手ぬぐいを巻き付けて枕にするんだけど、新品の手ぬぐいのおかげで非常によく寝れましたよ。






小屋に到着後、雨が降る前に水を取ってきたほうがよさそうだと思い水場へ……、この水場がまた遠いのよ。
梅花皮小屋という超立地のいい水場がある小屋を知っているため、本山小屋や御西小屋の結構下った場所にある水場がつらくて仕方がない。
本山小屋の水場はサンダルではいけません、登山靴を履いてしっかり岩場を下った先に水場があります……。



一応この水場で身体を拭ったんだけど水が冷たすぎて風邪をひくかと思いました、寒すぎです。




午後12時10分、昼食。
ラーメンを食べようとお湯を沸かしていると外が何やら騒がしい、屋根にたたきつけるような雨音……雨音!?
ついに来たかと窓から顔を出してみると土砂降りのような雨が急に降りだしていて、先に水を取りに行っておいてよかったと心の底から安堵しました。それと同時に、今日大日岳に登らなくて本当に良かったと……。



さらにこの後、昼食を食べた後は特にやることもないので、横になっているうちに寝てしまったらしい。気が付いたら午後5時くらいになっていた。






午後5時40分、本山小屋前。
寝袋にくるまり横になるうちに寝てしまったのか、気が付けば雨も上が外は夕方に。話を聞けば30分ほど前に雨が上がったんだとか、ちょうど雨が降っている間中寝ていたとは運が良い。
外に出てみればガスは多いものの見晴らしの良い景色が広がっています。そして夕焼けを見れそうだということで多くの登山者も稜線へと駆り出して展望を楽しんでいます。



とても景色がいいんだけど、雨上がりでブヨがすさまじい……。太陽の光もなくトンボが飛んでないのですごい数のブヨが人の周りを飛び盛っている。






雨上がりということで木々や高山植物の花は水滴を纏い魅力的な姿に、日暮れまでの間あたりをぶらぶらしながら他の登山者と談笑して時間をつぶします。


歓声が上がり振り返ってみると、なんと小屋の真上に二重の虹がかかっているではありませんか。久々に虹を見たのですがまさか二重!これはめったに見れないレアなものを見れたんじゃないでしょうか。
思わず超広角側のカメラに持ち替えて撮影してしまいました。周りの人々も一同カメラを虹に向けてしばしの間の奇跡を楽しんでいました。


午後6時10分、飯豊本山。
せっかくだから本山まで行ってみるかと思い小屋から本山までやってきてみるが……、日没のタイミングで晴れないかなと思っていたのですが……残念ながらガスは引かず。ダイクラ尾根を含めた北側の眺望が全くないのであきらめて小屋に戻ることに。



三脚撮影をやってみたけど、この記事を書くときに現像してみたら全くどれもだめでした、悔しい!


小屋へ戻ってきたタイミングで夕焼けが始まりました、山頂の向こうに湧き上がる雲が金色に染まり幻想的な光景が目の前に広がります。この時は小屋から「こんなに人いたの!?」というくらい人が出てきて……、みんなで夕焼けを眺めていました。



夕焼けのタイミングに焦っちゃってろくな写真が撮れなかったことが悔しい、また飯豊山登りに行きたいなぁ。






ブヨの猛烈なアタックをハッカスプレーで防ぎながら日没を眺め続けます。飯豊山で見た日没はアルプスなどよりも雲が近く、空との距離感が密接な気がしました。何というか、とても潤いに満ちた日没だったと思う。


真っ赤に染まる雲を見送り小屋に向かって振り向くとほぼ満月といえる月が空に浮かんでいた。
飯豊山二日目はガスから一時の快晴、そして土砂降りとなんだか目まぐるしい天気だったけども、終わりの夕日はとても美しく満足感にあふれた景色でしたとさ。
この後、小屋に戻り3日目に備えて就寝となるのですがびっくりするくらい早く寝れてしまい記憶がございません……。昼間に結構寝たんだけど、日ごろの疲れが出たのか翌日の明け方までぐっすりと寝すぎたわ……。
明日はついに復路、快晴の飯豊本山から大日岳を歩き、梅花皮小屋へと戻ります。


梅花皮小屋から飯豊本山までは飯豊山の核心部ともいえる「森林限界を超えた花の楽園」を歩き続けることができました。天狗の庭で雲が晴れ飯豊本山の山肌が明らかになったときの感動はこれまでの登山でも特に強く思い出に残ったいい景色です。
雪渓が残る山肌と咲き乱れるコバイケイソウやニッコウキスゲ、そして上空の青空……夏の飯豊山ここにありという景色を思う存分堪能することができました。







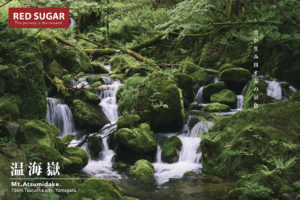



コメント